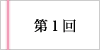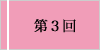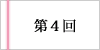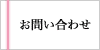第3回 「オンリーワン」のプロダクションを創る~ボンズの挑戦講師:南雅彦(株式会社ボンズ代表取締役・プロデューサー)2013年2月19日(火)18:30〜20:00(18:00開場予定)終了いたしました。講座のアーカイブはこちら | |
 「ストレンヂア」「カウボーイビバップ」など数々の名作を生み出し、作画の素晴らしさで定評のあるスタジオ ボンズ。「気骨のあるプロダクションを作りたい」として設立されたその存在感は大変大きく、アニメーションの次世代を切り開く旗手的役割を担っています。プロダクション、またはスタジオが個性を持ち、その個性がブランドになり、信用につながることで、次回作にもつながっていく。そういう好循環が、新たなコンテンツを作っていくのです。サンライズ社から独立し、独自のブランドを築き上げて来た南氏が、ボンズの設立から今日、そして将来への展望までを語ります。
南 雅彦(みなみ まさひこ)株式会社ボンズ 代表取締役・プロデューサー。 大阪芸術大学芸術学部映像計画学科卒業後、アニメ制作会社日本サンライズ(現サンライズ)に入社。「疾風!アイアンリーガー」「機動武闘伝Gガンダム」「天空のエスカフローネ」「カウボーイビバップ」等の作品をプロデューサーとして手掛ける。1998年に独立し、アニメーターの逢坂浩司、川元利浩と制作会社ボンズを設立。「COWBOY BEBOP 天国の扉」「ラーゼフォン」「鋼の錬金術師」「エウレカセブンAO」「絶園のテンペスト」などの作品をプロデュースしている。 |
|
講座アーカイブ
岡本美津子:今日は私が最も尊敬するプロデューサーのひとりであるボンズ[1]の南雅彦さんにお越しいただきました。南さんは大阪芸術大学を卒業され、アニメ制作会社のサンライズ[2](当時は日本サンライズ)に入社、「カウボーイビバップ」などを手がけられた後、1998年に独立し、制作会社ボンズを設立されました。ボンズでは「ラーゼフォン」、「鋼の錬金術師」、「交響詩篇エウレカセブン」など、皆さんもよくご存知の作品をたくさん手がけられています。今年で15周年を迎え、つねに業界のトップを走り続けてきたボンズの代表を務められている南さんに、今日はプロデューサーという役職についていろいろお話を伺えればと思っております。 南雅彦:もともと子供の頃からアニメが好きで、小学生のときに永井豪先生の「マジンガーZ」という巨大ロボットアニメーションがテレビで放映されていて楽しみに観ていました。普通は中学生になるとアニメから卒業したりするものですが、「宇宙戦艦ヤマト」が放映され、当時中学生だったわれわれは、本格的なSFものを志向した映像表現やストーリーに衝撃を受けました。さらに高校生になると、今度は「機動戦士ガンダム」が始まります。そういう具合に、アニメーションの表現のクオリティが上がっていく歴史とともに大人になってしまったので、いつのまにかこの業界に足を踏み入れたというのが正直なところです。 岡本:サンライズには制作進行として入られたとのことですが、そもそも制作進行というのはどういう業務を行なう役職なのでしょうか。 南:制作進行というのはラインプロデューサーだと思っています。作画の部分から完成までのラインを管理する仕事ですね。一概に管理と言っても、そのなかにはスケジュール管理、予算の管理、クオリティの管理などが含まれます。テレビシリーズですと一作品あたり、だいたい5人くらいの制作進行がいて、第1話を担当した者が第6話、第11話を担当する、というように話数ごとの分担制をとります。サンライズでは新入社員は全員、制作進行に配属されます。自分は富野監督に憧れていたので演出志望でサンライズに入ったのですが、数カ月後にはプロデューサー志望に変えていましたね。 岡本:それはどういうきっかけだったのですか。 南:当時はOVAなどのビデオパッケージもない時代で、基本的にテレビシリーズというのは、例えばロボットアニメであればロボットの玩具を売るためにつくられていました。そのさい、企画の段階からプロデューサーが玩具メーカーの意向を汲みながら作品をつくりあげていくという制作過程を目の当たりにして、監督だけで作品をつくっているわけではないのだと学び、今、自分の担当している制作進行の延長線上であるプロデューサーの仕事に魅力を感じるようになりました。 ◆「カウボーイビバップ」から独立まで岡本:その後1998年にサンライズさんから独立されるわけですが、そのあたりの経緯は? 南:独立したのは「カウボーイビバップ」の制作の途中になります。「カウボーイビバップ」は特殊な放送形態で、1クール12話分をテレビ東京で放送しました。諸事情により全部放映できなかったんです。第1話をやらずに第2話から始まったり、第4話から第6話までを飛ばしたりと、視聴者としてはいびつなかたちで放映されていたと感じたのではないでしょうか。その後WOWOWで全26話を放送しました。その間にサンライズを退社し、すぐに今の会社を立ち上げました。 岡本:最初はサンライズからお仕事をいただいたりしたんですか。 南:自分がプロデューサーをやった「天空のエスカフローネ」と「カウボーイビバップ」の劇場版(「COWBOY BEBOP 天国の扉」)に関しては、ウチのほうで制作を請け負ってやらせてもらいました。ただそれ以外は、基本的にはサンライズからの仕事は一切取らないでやっていこうと。それは自分たちに課していましたね。 岡本:またハードボイルドな(笑)。 南:だったらサンライズにいたままでもいいじゃないかというのがありましたから。「エスカフローネ」や「カウボーイビバップ」を一緒にやったバンダイビジュアルさんとの仕事も、最初はなるべく制限したいと考えていました。ボンズになって最初に手がけた「機巧奇傳ヒヲウ戦記」はバップさんと、次の「機動天使エンジェリックレイヤー」はエイベックスさん、角川書店さんとのお仕事です。意地を張っていた部分もあったのかもしれませんが、そこから始めないと独立した意味がないと思ったんですね。おかげで大変な思いもしました。あるメーカーのプロデューサーからは「ボンズなんてテレビ局に聞いても代理店に聞いても知らないんだよ。偉そうなことを言うな!」と言われたりと。一から関係性を始めなくてはいけないわけですから。 岡本:実際に南さんがプロデューサーとしてどういう仕事をされているのか、もう少し突っ込んで聞いてみたいと思うのですが、ボンズさんはオリジナル作品も多いですよね。プロデューサーとしてどのように企画を立ち上げられているのでしょうか。 南:原作ものであればストーリー、ドラマ、世界観全てが漫画や小説の中にありますが、オリジナルの場合は全てゼロからつくるわけですね。先ほども言ったように、昔は「ガンダムシリーズ」なども玩具を売るということが最大の目的でした。売り上げを上げるためにどういう展開ができるかというところから企画が進められていった。逆に言えば、玩具が売れるのであれば、どんなものをつくってもいいというわけではありませんが、アニメ制作もかなり自由な表現の場としてつくることができました。 岡本:でも「言うは易し」で、何がヒットするかわからないわけですよね。マーケティングなどはされているんですか。 南:すみません、プロデュース論と言いながら、実はマーケティングをちゃんとやったことがないんです(笑)。「カウボーイビバップ」を例にして言えば、監督の渡辺信一郎と脚本の信本敬子というのが、自分の3~4つ下の年代になるんですね。最初放送したとき「ルパン三世」に作風が似ているとよく言われるのですが、それも当然で、彼らは「ルパン」の初代の放送と被っている世代です。彼らと「こういうものがおもしろい」「こういうものをつくりたい」という話を何度もしながら、作品を組み立てていった。そういう意味では、同世代のマーケットに沿うような作品になっているという確信のようなものはありました。数字だけでなくプロデューサーとしての自分にはいってくる情報を咀嚼して創るべき作品を見据えていくとこがマーケティングに一番必要なことだと思います。 岡本:原作ものはどのように発掘されるのですか。 南:実はウチのほうからこういう原作ものがやりたいといって始めた作品はあまり多くないんです。出版社の人からこういう原作があるのでやってみないかというお話をいただくことのほうが圧倒的に多い。ただ、「鋼の錬金術師」に関して言うと、キャラクターデザインをやった伊藤嘉之君が自分で手がけたいと言って持ってきた企画です。まだコミックスで2巻までしか出ていないときだったのですが、読んでみると確かにゾクッとくるというか琴線に触れるものがあった。それですぐにエニックス(現スクウェア・エニックス)さんに連絡して、ぜひウチでアニメ化をさせてもらえないかという話をしました。 ◆プロデューサーのマネーマネージメント岡本:プロデューサーのもうひとつの大きな仕事として資金集めというものがありますね。よく海外の人から「なぜ日本では制作プロダクションが資金まで集めなくてはならないんだ」と訊かれ、答えに困るのですが、その辺はどのように行なわれるのでしょうか。 南:もともとアニメは、一般的にはテレビ局から出る放送権料でつくられていたのですが、制作コストが上がったのと、そもそもスポンサーの間口が狭いんですよね。だいたい玩具メーカーかお菓子メーカーが多いのですが、そうなると限られた作品にしか放送できないですよね。また、われわれの場合は、ビデオメーカーやレコード会社にスポンサーになっていただくことが多いのですが、それほど大きなスポンサー料をかけられないという事情もあり、放送権料だけではとても制作ができなかったりします。 岡本:ボンズさん自身も出資されていますよね。それは権利をなるべく確保していくためなのでしょうか。 南:そうですね。オリジナル作品の場合は、ウチは出資することにより出版窓口を持っていて、小説や漫画になるときにはすべてチェックします。また、契約書に関してしっかりと読み取っていく事もプロダクションにとって大事だと考えています。 南:先ほどのアニメーションの制作費ですが、ほとんど純粋な制作費で消えてしまうんですね。本来なら、製造業であれば20~30%を販管費に充て、それ以外を製作費に回すというのが正しいやり方だと思うのですが、なかなかその範囲でつくることは難しい。ひとつ上のクオリティを目指そうとすると、それ相応の予算が制作費に乗っかってきますから、映像がビジネスになっていくさいに二次的な収益がきちんと確保できるように動く必要があります。それによってクリエイターの報酬も大きくなり、作品のクオリティも上がるわけですから、プロダクションが契約をチェックし権利を主張することはとても大切なことだと思っています。 岡本:先ほど出版窓口のお話をされていましたけれど、ボンズさん自身も、二次的な展開を考えていらっしゃるわけですよね。 南:映像がビジネスに結びついていくことが第一ですけれど、今はSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のゲームなどの収益が上がってきているという話は聞いています。ウチでは上がっているものはないのですが、いくつかの作品などは非常に大きなビジネスに結びついていると聞いてはいます。 岡本:DVDなどのパッケージはどうですか。 南:昔に比べると売り上げは下がってきています。以前であれば3万本以上売れれば大成功だと言われていたのですが、そういうタイトルはかなり少なくなっている。今では1万本売れれば成功だと言われるくらいです。ちょっと寂しい話ですが。 岡本:海外へのビジネス展開についてはどのように考えていらっしゃいますか。 南:「クールジャパン」だ「グローバル展開」だと騒がれて久しいですが、プロダクションの多くは中小のスタジオで、単独で海外展開できているような会社はほとんどないのが現状です。もちろん製作委員会を通じて海外展開に長けている会社、窓口になったりパッケージビジネスをやったり配信をやったりするような会社がパートナーとなって行っています。プロダクション単体でビジネスが成立しているという話はあまり聞かないですね。 ◆ボンズがオリジナル作品に挑戦する理由岡本:最近は漫画を原作としたアニメは非常に堅調である一方、オリジナルのアニメが減っているのではないかと危惧する部分もあります。そのようななかで、ボンズさんはなぜ果敢にオリジナル作品に挑戦されるのでしょうか。ヒットしないかもしれないというリスクもあるわけですよね。  南:自分なりに考えるところを言いますと、原作ものの場合は、すでにその作品に触れている方が何百万人も居て最初から何をつくるべきかはっきりと決まっているわけですね。漫画であれ小説であれ、読者がこれくらいいて、こういうところをおもしろがっていて……という軸になる部分があって、それをどうアニメーションという映像で表現していくかが問われます。オリジナルは当然そういう軸になるものがないわけですね。ですから、自分たちがどういうものをつくりたいんだというヴィジョンがないとつくれない。作り手の欲の部分と言ってもいいかもしれません。お客さんと戦っているわけではないのですが、オリジナルアニメというのはどう見てもらえるのか、どう感じてもらえるのかというところを日々模索しながらつくらなければならないわけで、結局そういうところがオリジナルアニメーションを制作することなのでしょうね。 岡本:オリジナル作品をつくるにあたって、ボンズさんのなかで企画会議はけっこうされるんですか。 南:それは日々やっていますね。プロデューサーが企画を提案してスタッフを招集するケースもありますし、スタッフのほうからこういうものをつくりたいと言って動き出す企画もあります。例えば「STAR DRIVER 輝きのタクト」は、もともとは監督の五十嵐卓哉君がオリジナルのロボットアニメをやりたいと言って始まった企画です。私はサンライズに在籍していたので、自分がつくると「エウレカセブン」や「ラーゼフォン」のように、リアルロボットアニメーションの路線になる。もともとは「ガンダム」や「イデオン」が好きでこの業界にはいったわけですから。ところが五十嵐監督は、ロボットアニメーションというジャンルで青春ものをやりたいと言うわけです。自分にはその発想がない、自分とは違ったところからアプローチしてくる。オリジナルアニメの場合は意外とそういうところがあります。 岡本:企画会議はどんな感じで行なわれるんですか。何月何日にやるからそれぞれアイディアを持ち寄ってくれと通達したりするんですか。 南:それだとなぜかあまりいい企画が集まらないんですよ。ひとつお題を与えて、いつでもいいから考えておいでと言って投げたほうが、おもしろい企画が出てきますね。とはいえ、企画は所詮企画なんですよね。資金集めとかパートナー集めとかスタッフ集めとか、企画を現実化させていくほうが、企画を考えるよりも10倍も20倍も大変です。逆に言うとそこまで企画を詰めることができれば、オリジナル作品として魅力的なものがおのずと浮かび上がってくると思っています。 岡本:企画開発力をスタジオが持っているという点がボンズさんの強みと言いますか、ボンズのボンズたる所以だと思っています。ブランド力を維持する秘訣のようなものがあれば、教えていただけないでしょうか。 南:これは一見昔ながらの意見に聞こえるかもしれませんが、一緒に仕事をする人間たちとお酒を飲んで、面と向かってああでもないこうでもないとやり合うことは、とても大切なことだと思っています。アニメーションというのはたくさんの人の手によってつくられるものです。クリエイターだけではなくて、時にはビデオメーカーやテレビ局の人たちも交えて喧々諤々やり合い、つかみ合いの一歩寸前のところまでいくこともあります。制作に携わる多くの人たちには、それぞれ生きてきたバックグラウンドがあり、いろいろな考え方を持っている。それをぶつけ合うことが好きなんですね。 [脚注]
| |